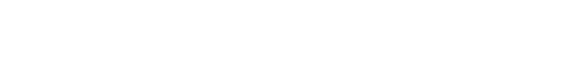神経再生・創薬研究部門
研究内容概略
中枢神経系は一度傷ついてしまうと再生が非常に困難な組織です。外傷性脳損傷や脊髄損傷により失った神経組織は自己で回復することはできません。我々はiPS細胞を用いて神経系の各種細胞を作成し、それらを移植することで神経再生に挑んでいます。
また、様々な神経変性疾患患者様の血球や皮膚組織からiPS細胞を作成し、ニューロンやアストロサイト、ミクログリア、さらには脳オルガノイド(ミニチュア脳)を誘導して創薬研究を行っています。その他にも神経新生や老化研究も行っており、世界に新発見を発信しています。基礎と臨床の連携を密にして患者様に還元できる研究を行なっています。
メンバー紹介
-

-
岡野 栄之 客員教授
これまでに主に慶應義塾大学にて脊髄損傷の再生治療、神経変性疾患のA L Sやアルツハマー病の創薬・治療研究に携わってまいりました。共に臨床治験の段階まで進めることができ、社会実装の手前まで押し進めています。藤田医科大学でも同様に幅広く神経再生、創薬研究を進めてまいります。
-

-
加瀬 義高 講師
再生医療、老化、創薬をキーワードにし、外傷性脳損傷の再生、軸索再生、老化制御研究、そして各種疾患に対する創薬研究を展開しています。我々はこれらテーマに関する特許や論文を積極的に発表しています。藤田医科大学においては、中枢神経系の再生治療を実臨床に応用可能な段階まで推し進めることを目指しています。
-

-
石川 充 講師
精神疾患/神経発達障害の病態を細胞モデルで提示するのは挑戦的な側面があります。私は、バイオエンジニアリング技術を基盤にES/iPS細胞から様々な分化細胞モデルを作出したり、再生医療や創薬に応用できる遺伝子導入技術開発に力を入れることで、この挑戦的な課題に取り組んでいるところです。
-

-
渡部 博貴 講師
これまで、ハーバード大学や慶應義塾大学において、アルツハイマー病の原因遺伝子や遺伝的素因に関する研究に従事し、マウスやiPS細胞などのモデルを用いて、その病態メカニズムを解析してまいりました。藤田医科大学では、これらの研究をさらに発展させ、認知症患者の皆様に希望をもたらす創薬研究に取り組んでいく所存です。
-

-
馬渕 洋 連携研究員(藤田医科大学東京 先端医療研究センター 准教授)
私はこれまで、生体内に存在する組織幹細胞の機能解析に情熱を注いできました。神経組織を含むさまざまな組織再生において、間葉系細胞が極めて重要な役割を果たしていることが明らかになってきています。こうした細胞が織りなす複雑なネットワークを理解し、その応答性に外部から働きかけることができれば、再生医療の可能性は飛躍的に広がると確信しています。私は、このメカニズムを解き明かし、再生治療を一歩先へと押し進めることを目指して、全力で研究に取り組んでいきます。
-

-
Sopak Supakul 助教
タイ出身で、日本の医学部を卒業後、大学院(慶應義塾大学岡野研)にて医学博士号を取得し、本学に着任しました。幹細胞およびiPS細胞を駆使した革新的な神経疾患の研究に没頭してまいりました。ベンチからベッドサイドへのブレークスルーな研究開発を展開し、新たな治療法の提供に貢献していくことを志しております。