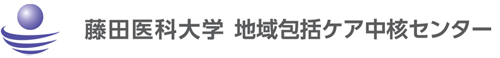プログラム開催レポート
第5回
日時:2025年2月4日(火)、10日(水)
会場:オンライン(10日はウェビナー)
プログラム:「最終報告 実践報告とこれから」
<1日目>参加自治体、オブザーバーのみ
参加自治体成果報告(各自治体15分)
○自治体名「発表題名」
(最終テーマカテゴリー)
○新潟県阿賀野市「「もう年だから…」と諦めない!〜これが阿賀野の進む道〜」
(望む活動や暮らしを可能にする支援のあり方 (総合事業、自立支援))
○長野県箕輪町「その人のふつうの暮らしを支える介護予防を通じた地域づくり」
(望む活動や暮らしを可能にする支援のあり方 (総合事業、自立支援))
メンターコメント 岩名礼介 氏 服部真治 氏 都築晃 氏
休憩
○島根県安来市「それぞれの幸せのカタチを求めてー「始める」気持ちをつくるー」
(高齢者の多様な活動、参加の場 (ポピュレーション))
○愛知県東海市「高齢者の望む暮らしを軸とした自立支援チームワーク」
(虚弱高齢者への専門的支援後の活動)
メンターコメント 三原岳 氏 服部真治 氏 都築晃 氏
休憩
○福島県喜多方市「高齢者になっても役割を持ち安心して暮らし続けられるまち喜多方市をめざして」
(地域の支え合いの体制づくり (生活支援体制))
○広島県福島市「福山市の重層的支援体制整備事業における多機関協働の在り方」
(包括的支援体制(重層・多機関協働))
メンターコメント 亀井善太郎 氏 三原岳 氏 高橋拓朗 氏
休憩
○青森県平内町「共に歩み、支え合う町を目指して」
(支援が必要な高齢者の発見、見守り (孤立・孤独))
○福島県須賀川市「「まだできる」応援プロジェクト」
(虚弱高齢者の望む活動・暮らし・生きがいを支援 (総合事業、自立支援、生活支援))
メンターコメント 亀井善太郎 氏 岩名礼介 氏 高橋拓朗 氏
休憩
○新潟県田上町「やりたい」ことが宣言でき本人の「やりたい」を叶えよう〜自由な暮らしを取り戻す〜」
(虚弱高齢者の望む活動・暮らし・生きがいを支援 (総合事業、自立支援、生活支援))
○島根県邑南町「やれんこと(困りごとや不安)があっても、自宅で安心して暮らすことを望める邑南町」
(安心して住み続けられるための支援のあり方 (Aging in Place))
メンターコメント 亀井善太郎 氏 三原岳 氏 高橋拓朗 氏
休憩
修了式
パートナー挨拶 稲垣圭亮 氏 竹田哲規 氏 坂上遼 氏 野々山紗矢果 氏
メンター挨拶 池田寛 氏 高橋拓朗 氏 三原岳 氏 岩名礼介 氏 松本小牧 氏 亀井善太郎 氏
修了証授与・主催者挨拶 都築晃 氏
<2日目>ウェビナーにて
成果報告会「〜確かな手ごたえと成果を導く動的な地域包括ケアへ〜成功の好循環が生まれる政策形成の秘訣」
厚生労働省挨拶
厚生労働省 老健局 総務課 課長補佐 小西雄樹 氏
事業紹介・報告
藤田医科大学地域包括ケア中核センター 都築晃 氏
プログラム参加自治体 成果報告・インタビュー
進行:藤田医科大学地域包括ケア中核センター 池田寛 氏
解説:NTTデータ経営研究所 高橋拓朗 氏
《成果報告》*発表テーマは1日目と同じ
阿賀野市、福山市、平内町、須賀川市
《インタビュー》
喜多方市、田上町、箕輪町、東海市、安来市、邑南町
総合討論
《登壇者》
厚生労働省 老健局 総務課 課長補佐 菊池一 様
三菱UFJリサーチ&コンサルティング 岩名礼介 氏
PHP総研 亀井善太郎 氏
医療経済研究機構 服部真治 氏
NTTデータ経営研究所 高橋拓朗 氏
ニッセイ基礎研究所 三原岳 氏(モデレーター)
=========================================================
会場:オンライン(10日はウェビナー)
プログラム:「最終報告 実践報告とこれから」
<1日目>参加自治体、オブザーバーのみ
参加自治体成果報告(各自治体15分)
○自治体名「発表題名」
(最終テーマカテゴリー)
○新潟県阿賀野市「「もう年だから…」と諦めない!〜これが阿賀野の進む道〜」
(望む活動や暮らしを可能にする支援のあり方 (総合事業、自立支援))
○長野県箕輪町「その人のふつうの暮らしを支える介護予防を通じた地域づくり」
(望む活動や暮らしを可能にする支援のあり方 (総合事業、自立支援))
メンターコメント 岩名礼介 氏 服部真治 氏 都築晃 氏
休憩
○島根県安来市「それぞれの幸せのカタチを求めてー「始める」気持ちをつくるー」
(高齢者の多様な活動、参加の場 (ポピュレーション))
○愛知県東海市「高齢者の望む暮らしを軸とした自立支援チームワーク」
(虚弱高齢者への専門的支援後の活動)
メンターコメント 三原岳 氏 服部真治 氏 都築晃 氏
休憩
○福島県喜多方市「高齢者になっても役割を持ち安心して暮らし続けられるまち喜多方市をめざして」
(地域の支え合いの体制づくり (生活支援体制))
○広島県福島市「福山市の重層的支援体制整備事業における多機関協働の在り方」
(包括的支援体制(重層・多機関協働))
メンターコメント 亀井善太郎 氏 三原岳 氏 高橋拓朗 氏
休憩
○青森県平内町「共に歩み、支え合う町を目指して」
(支援が必要な高齢者の発見、見守り (孤立・孤独))
○福島県須賀川市「「まだできる」応援プロジェクト」
(虚弱高齢者の望む活動・暮らし・生きがいを支援 (総合事業、自立支援、生活支援))
メンターコメント 亀井善太郎 氏 岩名礼介 氏 高橋拓朗 氏
休憩
○新潟県田上町「やりたい」ことが宣言でき本人の「やりたい」を叶えよう〜自由な暮らしを取り戻す〜」
(虚弱高齢者の望む活動・暮らし・生きがいを支援 (総合事業、自立支援、生活支援))
○島根県邑南町「やれんこと(困りごとや不安)があっても、自宅で安心して暮らすことを望める邑南町」
(安心して住み続けられるための支援のあり方 (Aging in Place))
メンターコメント 亀井善太郎 氏 三原岳 氏 高橋拓朗 氏
休憩
修了式
パートナー挨拶 稲垣圭亮 氏 竹田哲規 氏 坂上遼 氏 野々山紗矢果 氏
メンター挨拶 池田寛 氏 高橋拓朗 氏 三原岳 氏 岩名礼介 氏 松本小牧 氏 亀井善太郎 氏
修了証授与・主催者挨拶 都築晃 氏
<2日目>ウェビナーにて
成果報告会「〜確かな手ごたえと成果を導く動的な地域包括ケアへ〜成功の好循環が生まれる政策形成の秘訣」
厚生労働省挨拶
厚生労働省 老健局 総務課 課長補佐 小西雄樹 氏
事業紹介・報告
藤田医科大学地域包括ケア中核センター 都築晃 氏
プログラム参加自治体 成果報告・インタビュー
進行:藤田医科大学地域包括ケア中核センター 池田寛 氏
解説:NTTデータ経営研究所 高橋拓朗 氏
《成果報告》*発表テーマは1日目と同じ
阿賀野市、福山市、平内町、須賀川市
《インタビュー》
喜多方市、田上町、箕輪町、東海市、安来市、邑南町
総合討論
《登壇者》
厚生労働省 老健局 総務課 課長補佐 菊池一 様
三菱UFJリサーチ&コンサルティング 岩名礼介 氏
PHP総研 亀井善太郎 氏
医療経済研究機構 服部真治 氏
NTTデータ経営研究所 高橋拓朗 氏
ニッセイ基礎研究所 三原岳 氏(モデレーター)
=========================================================
1)参加自治体成果報告
「実践報告とこれから」とテーマとし、全参加自治体がプログラム期間を通じて検討した課題解決ストーリー、ファーストステップを共有することで他自治体から地域の課題解決において持つべき着眼点や、望ましい変化を起こすための仕掛けのヒントを得ることを目的とした。
発表にあたり、「検討プロセスを「プログラムに参加していない関係者」にも伝え賛同を得られるようにすること」、つまり、この発表のためだけに資料を作るのではなく、庁内外、それぞれの地域の地域包括ケアに関わる関係者にそのまま説明できる資料作りを促した。
参加自治体はそれぞれ、各回の動画やフォローアップの音声を聞き返し、自分達がどのように考えていて、どう変わってきたのかを振り返り、気づかないうちに変わりたどり着いた自分達の考えとその変遷に改めて気づき、半年間の成果について堂々と発表した。
2自治体毎で担当したメンターが感想や今後についてのエールを送った。
「実践報告とこれから」とテーマとし、全参加自治体がプログラム期間を通じて検討した課題解決ストーリー、ファーストステップを共有することで他自治体から地域の課題解決において持つべき着眼点や、望ましい変化を起こすための仕掛けのヒントを得ることを目的とした。
発表にあたり、「検討プロセスを「プログラムに参加していない関係者」にも伝え賛同を得られるようにすること」、つまり、この発表のためだけに資料を作るのではなく、庁内外、それぞれの地域の地域包括ケアに関わる関係者にそのまま説明できる資料作りを促した。
参加自治体はそれぞれ、各回の動画やフォローアップの音声を聞き返し、自分達がどのように考えていて、どう変わってきたのかを振り返り、気づかないうちに変わりたどり着いた自分達の考えとその変遷に改めて気づき、半年間の成果について堂々と発表した。
2自治体毎で担当したメンターが感想や今後についてのエールを送った。
2)修了式
日程はもう1日あるが、公開セミナーとなるため、全参加自治体が各々の成果報告を行ったこの日に修了式を行った。
プログラムに参加し、日常の業務と並行して苦労をして考えてきたことを画面越しにそれぞれ讃えあい、全国に仲間がいると心強く感じられる瞬間となった。
日程はもう1日あるが、公開セミナーとなるため、全参加自治体が各々の成果報告を行ったこの日に修了式を行った。
プログラムに参加し、日常の業務と並行して苦労をして考えてきたことを画面越しにそれぞれ讃えあい、全国に仲間がいると心強く感じられる瞬間となった。
(2日目・ウェビナー)
3)事業紹介・報告
報告者:藤田医科大学地域包括ケア中核センター 都築晃
本プログラムについて紹介・報告を事業主体である藤田医科大学より行った。
3)事業紹介・報告
報告者:藤田医科大学地域包括ケア中核センター 都築晃
本プログラムについて紹介・報告を事業主体である藤田医科大学より行った。
4)参加自治体による成果報告(4市町)・参加自治体へのインタビュー(6市町)
1日目に行った発表から、各テーマや各自治体の構成から特徴的な4市町村を選抜し発表を行った。また、それ以外の参加自治体からこの間に自分達が何に気付き、何を考え、どう動き、これからどうするのかなどについて聞いた。
1日目に行った発表から、各テーマや各自治体の構成から特徴的な4市町村を選抜し発表を行った。また、それ以外の参加自治体からこの間に自分達が何に気付き、何を考え、どう動き、これからどうするのかなどについて聞いた。
5)総合討論
当プログラムメンター陣とゲストスピーカーとして小西雄樹氏(厚生労働省老健局総務課課長補佐)が登壇し、成果報告をした4市町の内容を例に出しながら、本プログラムの根幹であるメンタリングについて、メンター陣が何を考え、何を伝えたか、などが語られた。
大きな社会的問題は共通しているが、それぞれ自治体の状態や変化、リソースなどが異なるため、共有された資料だけでなく「何が起こっていて(WHAT)」「どうしてそうなっているのか(WHY)」をよく聞き取って「解決するためにはどうするのか(HOW)」をともに考え、「そしてどうなるのか(SO WHAT)」を予測して次に繋げることを繰り返し、寄り添って伴走したことがわかる討議であった。
当プログラムメンター陣とゲストスピーカーとして小西雄樹氏(厚生労働省老健局総務課課長補佐)が登壇し、成果報告をした4市町の内容を例に出しながら、本プログラムの根幹であるメンタリングについて、メンター陣が何を考え、何を伝えたか、などが語られた。
大きな社会的問題は共通しているが、それぞれ自治体の状態や変化、リソースなどが異なるため、共有された資料だけでなく「何が起こっていて(WHAT)」「どうしてそうなっているのか(WHY)」をよく聞き取って「解決するためにはどうするのか(HOW)」をともに考え、「そしてどうなるのか(SO WHAT)」を予測して次に繋げることを繰り返し、寄り添って伴走したことがわかる討議であった。
参加者(参加自治体)の声(アンケート結果より一部抜粋)
第5回プログラムでどんな気づきがありましたか?自分たちの最終報告のとりまとめの過程で感じたこと や、他自治体の報告を聞いて感じたことをできるだけ詳しく教えてください
・自分の自治体の発表において感じたことは、意識の変化です。半年前のチームでは、これもできていない、あれもできていないと諦め、自分達を責めていました。しかしアジャイルのプログラムを通して出来ることに目を向けるようになったことで、仕事に対するモチベーション、向かい方や戦い方が本当に変わったと感じます。この半年間、とても悩み、モヤモヤもしました。でもそのおかげでチームメンバー内の協力や連携も強くなったと思います。
・他の自治体の報告内容がすごい!と感動しました。報告を聞いて、そちらはそういうことに悩み、取り組んでいたのですね、とわかりました。
・まとめをするなかで、多少忘れかけていたこともありましたが、最終報告資料を作成し、チームとしてやるべきことを見つけていく過程を再認識できました。他自治体報告では、悩んだり迷ったりした変遷がよくわかり、自分事のように聞かせていただきました。
・他の自治体の報告を聞き、オリエンテーションのときとは見違えるぐらい自信たっぷりに発表しているなと感じました。
・自分たちの考えの変化、なぜそう思うに至ったかの道のりをチーム以外の方(喜多方市は地域包括 支援センターやケアマネジャーに説明するイメージで作成)にわかりやすく伝えるにはどうしたらよいか、 構成を考えるのに時間がかかりましたが、振り返りながらまとめたことで、このあと自治体内外で説明する際に使える内容になったと思います。
・最終報告のまとめをする過程で、改めてこれまでの過程を振り返ることができた。
・当市以外の自治体が報告した内容は、どれも当市がいずれ取り組まなければならないものであり、これからもともに学んだ自治体や先行自治体の様子から目が離せないと感じた。
・似たような課題やありたい姿だなと思っても取り組む内容が違っており、総合事業や地域支援事業が市町村の実情に合わせて実施ということに「そういうことか」と気づくことができました。
・ただの「通過点に過ぎない」思いです。これからのアクションが重要だと思うので、今後も各方面と対話をしながら進めていきたいです。
・他の自治体の報告を聞いて、行政の方がこんなに真剣に自分の町について考えに考えていることに驚きました。
・最初はなにがなんだか状態でしたが、今、動き出して"これかっ"という感じ。今日も早速、動いてきます。
・自分達のまとめをする中で、エントリーをした頃から最終のまとめをするまでの、考えたことや思いの変化を振り返ることができ、考え方が大きく変化、成長したと感じました。
・国から次々とくるさまざまな施策に対応してきたものが、施策に取り組むことが目的になっていて、活用されてないもの、活用できないものも多々あり、アジャイルを知ってしまったので、修正したい!!という衝動に駆られています。
第5回プログラムでどんな気づきがありましたか?自分たちの最終報告のとりまとめの過程で感じたこと や、他自治体の報告を聞いて感じたことをできるだけ詳しく教えてください
・自分の自治体の発表において感じたことは、意識の変化です。半年前のチームでは、これもできていない、あれもできていないと諦め、自分達を責めていました。しかしアジャイルのプログラムを通して出来ることに目を向けるようになったことで、仕事に対するモチベーション、向かい方や戦い方が本当に変わったと感じます。この半年間、とても悩み、モヤモヤもしました。でもそのおかげでチームメンバー内の協力や連携も強くなったと思います。
・他の自治体の報告内容がすごい!と感動しました。報告を聞いて、そちらはそういうことに悩み、取り組んでいたのですね、とわかりました。
・まとめをするなかで、多少忘れかけていたこともありましたが、最終報告資料を作成し、チームとしてやるべきことを見つけていく過程を再認識できました。他自治体報告では、悩んだり迷ったりした変遷がよくわかり、自分事のように聞かせていただきました。
・他の自治体の報告を聞き、オリエンテーションのときとは見違えるぐらい自信たっぷりに発表しているなと感じました。
・自分たちの考えの変化、なぜそう思うに至ったかの道のりをチーム以外の方(喜多方市は地域包括 支援センターやケアマネジャーに説明するイメージで作成)にわかりやすく伝えるにはどうしたらよいか、 構成を考えるのに時間がかかりましたが、振り返りながらまとめたことで、このあと自治体内外で説明する際に使える内容になったと思います。
・最終報告のまとめをする過程で、改めてこれまでの過程を振り返ることができた。
・当市以外の自治体が報告した内容は、どれも当市がいずれ取り組まなければならないものであり、これからもともに学んだ自治体や先行自治体の様子から目が離せないと感じた。
・似たような課題やありたい姿だなと思っても取り組む内容が違っており、総合事業や地域支援事業が市町村の実情に合わせて実施ということに「そういうことか」と気づくことができました。
・ただの「通過点に過ぎない」思いです。これからのアクションが重要だと思うので、今後も各方面と対話をしながら進めていきたいです。
・他の自治体の報告を聞いて、行政の方がこんなに真剣に自分の町について考えに考えていることに驚きました。
・最初はなにがなんだか状態でしたが、今、動き出して"これかっ"という感じ。今日も早速、動いてきます。
・自分達のまとめをする中で、エントリーをした頃から最終のまとめをするまでの、考えたことや思いの変化を振り返ることができ、考え方が大きく変化、成長したと感じました。
・国から次々とくるさまざまな施策に対応してきたものが、施策に取り組むことが目的になっていて、活用されてないもの、活用できないものも多々あり、アジャイルを知ってしまったので、修正したい!!という衝動に駆られています。
参加者(成果報告会聴講者)の声(アンケート結果より一部抜粋)
来年度以降、このプログラムが開催されたら参加したいと思いますか
<ぜひ参加したい>
・現状、日々の業務を行いながら内部だけで取り組むべき課題やそのアプローチを考えていくことはなかなか難しいと感じているので、外部からの意見も取り入れ現状打破ができればいいなと思います。
・卒業自治体向けのプログラムもお願いしたいです。
・6年間現場最前線で活動していますが、未だ委託先としての当法人の活動への理解がなく、委託元の市へ現状を伝えても特に行政説明もなく孤立感の中、市内 4 つの包括(すべて異なる法人) でどのように SC 活動をしていけばよいか?この先が見えなくなっていたため。
・令和 5年度に参加しましたが、10 期計画に向けて、他の職員にも勧めたいですし、包括支援センターと参加したい気持ちです。
・参加したいですが、自治体関係者ではないので残念です
・このままではいけないのでは・・・と思いながら仕事しており、参加をきっかけに少しでも変わりたいと思っ た。同じ思いの仲間を増やしていきたいと思った。
<どちらかというと参加したい>
・チームを作って参加することが難しい。
・職員が3年ごと異動しています。当市の課題が見えてきた頃に異動になるため、なかなか施策が進んでいきません。ロジックを整理すれば職員が変わっても施策を進めていけると感じました。
・プログラムの魅力はわかるが、人員不足の中で、対応できるのかが不安である。
・地域ケア会議のあり方、他機関との自立支援の共通認識への課題をもっており、どのように介入すればよいかヒントが欲しい。
・とても興味はあるが、次年度他の計画(アドバイザー派遣等)もあるため悩む。
・共通理解を深めたり、政策の合意形成のための手段として有効だと感じたから
・関係者で集まって考える、そんなシンプルなことに取り組めないでいるのが現実です。これを機会に取り組めるのではと思いました。
・今やっている事業に追われて、モヤモヤがあるので、関係者皆でロジックモデルで考えてみたい。
<どちらとも言えない>
・人事異動があるため、もし来年も在籍すれば参加を検討したい。
・このプログラムは魅力的だが、今のメンバーでできる気がしない。
・人事が不明であるため
・上司に相談していないので
・行政と一緒に研修に参加していないので、委託を受けている包括からはどうとも言えない。
・まだ本市のおかれている状況や施策が理解できておらず、ある程度理解が進んでから希望したいと考えているため。
<どちらかというと参加したくない>
・関係者が多く、難しく思える。
・現状では参加が必要とは考えていないため。
・来年度は新規事業開始等新たな取り組みもあり、そちらの対応や課題抽出、その解決等に追われることになると思われるため。
<全く参加したくない>
・本報告等で共有して頂くだけで充分であるため。
<市町村・自治体関係者ではない>
・職種が違うため。時間が合えば今後も参加したい。
・市町村に情報を共有したいです。
来年度以降、このプログラムが開催されたら参加したいと思いますか
<ぜひ参加したい>
・現状、日々の業務を行いながら内部だけで取り組むべき課題やそのアプローチを考えていくことはなかなか難しいと感じているので、外部からの意見も取り入れ現状打破ができればいいなと思います。
・卒業自治体向けのプログラムもお願いしたいです。
・6年間現場最前線で活動していますが、未だ委託先としての当法人の活動への理解がなく、委託元の市へ現状を伝えても特に行政説明もなく孤立感の中、市内 4 つの包括(すべて異なる法人) でどのように SC 活動をしていけばよいか?この先が見えなくなっていたため。
・令和 5年度に参加しましたが、10 期計画に向けて、他の職員にも勧めたいですし、包括支援センターと参加したい気持ちです。
・参加したいですが、自治体関係者ではないので残念です
・このままではいけないのでは・・・と思いながら仕事しており、参加をきっかけに少しでも変わりたいと思っ た。同じ思いの仲間を増やしていきたいと思った。
<どちらかというと参加したい>
・チームを作って参加することが難しい。
・職員が3年ごと異動しています。当市の課題が見えてきた頃に異動になるため、なかなか施策が進んでいきません。ロジックを整理すれば職員が変わっても施策を進めていけると感じました。
・プログラムの魅力はわかるが、人員不足の中で、対応できるのかが不安である。
・地域ケア会議のあり方、他機関との自立支援の共通認識への課題をもっており、どのように介入すればよいかヒントが欲しい。
・とても興味はあるが、次年度他の計画(アドバイザー派遣等)もあるため悩む。
・共通理解を深めたり、政策の合意形成のための手段として有効だと感じたから
・関係者で集まって考える、そんなシンプルなことに取り組めないでいるのが現実です。これを機会に取り組めるのではと思いました。
・今やっている事業に追われて、モヤモヤがあるので、関係者皆でロジックモデルで考えてみたい。
<どちらとも言えない>
・人事異動があるため、もし来年も在籍すれば参加を検討したい。
・このプログラムは魅力的だが、今のメンバーでできる気がしない。
・人事が不明であるため
・上司に相談していないので
・行政と一緒に研修に参加していないので、委託を受けている包括からはどうとも言えない。
・まだ本市のおかれている状況や施策が理解できておらず、ある程度理解が進んでから希望したいと考えているため。
<どちらかというと参加したくない>
・関係者が多く、難しく思える。
・現状では参加が必要とは考えていないため。
・来年度は新規事業開始等新たな取り組みもあり、そちらの対応や課題抽出、その解決等に追われることになると思われるため。
<全く参加したくない>
・本報告等で共有して頂くだけで充分であるため。
<市町村・自治体関係者ではない>
・職種が違うため。時間が合えば今後も参加したい。
・市町村に情報を共有したいです。
第4回
日時:2024年12月23日(月)、25日(水)
会場:オンライン
プログラム:「実践と成功の手ごたえをつかむ」
<1日目>
講義「アジャイル型政策形成 補論」&トークセッション
亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
グループワーク「課題解決ストーリーブラッシュアップ」
<2日目>
グループワーク「コミュニティビルディング」
グループワーク「ネクストアクションを考える」
=========================================================
会場:オンライン
プログラム:「実践と成功の手ごたえをつかむ」
<1日目>
講義「アジャイル型政策形成 補論」&トークセッション
亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
グループワーク「課題解決ストーリーブラッシュアップ」
<2日目>
グループワーク「コミュニティビルディング」
グループワーク「ネクストアクションを考える」
=========================================================
1)講義「アジャイル型政策形成 補論」&トークセッション
講師:亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
これまでに学んできた「アジャイル型政策形成」についてまとめと補足として話があった。
まさに「アジャイル」で動いてきた数ヶ月を振り返って、改めて「アジャイルに進める」とは何かということと、それを可視化するためツールとしての「ロジックモデル」の考え方について説明があった。
後半のトークセッションではこれからどうしていくか不安な点も含めて理解を深めるために参加自治体より質問を受けた。
本プログラムの特徴である、各回の録音・録画を聞き返すことで、メンターが何を聴き、何に反応しているのかを知って自分の思考について気づくことを勧められた。
講師:亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
これまでに学んできた「アジャイル型政策形成」についてまとめと補足として話があった。
まさに「アジャイル」で動いてきた数ヶ月を振り返って、改めて「アジャイルに進める」とは何かということと、それを可視化するためツールとしての「ロジックモデル」の考え方について説明があった。
後半のトークセッションではこれからどうしていくか不安な点も含めて理解を深めるために参加自治体より質問を受けた。
本プログラムの特徴である、各回の録音・録画を聞き返すことで、メンターが何を聴き、何に反応しているのかを知って自分の思考について気づくことを勧められた。
2)グループワーク「課題解決ストーリーブラッシュアップ」
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
同席パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:箕輪町、阿賀野市、安来市
B:福山市、東海市、喜多方市
C:平内町、須賀川市、邑南町、田上町
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
同席パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:箕輪町、阿賀野市、安来市
B:福山市、東海市、喜多方市
C:平内町、須賀川市、邑南町、田上町
3)グループワーク「コミュニティビルディング」
担当メンター
1:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
2:三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
同席パートナー
1:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)、稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
2:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
1:箕輪町、阿賀野市、安来市、福山市、東海市、喜多方市
2:平内町、須賀川市、邑南町、田上町
メンタリングであまり接しなかったメンターとグループを組みコミュニケーションをとった。
前半は各個人が本プログラムに参加してどう変化があったか、後半はチームとしてあった変化は何かをテーマとしながらもそれぞれのグループで自由な発言を求め、コミュニティビルディングを図った。
担当メンター
1:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
2:三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
同席パートナー
1:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)、稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
2:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
1:箕輪町、阿賀野市、安来市、福山市、東海市、喜多方市
2:平内町、須賀川市、邑南町、田上町
メンタリングであまり接しなかったメンターとグループを組みコミュニケーションをとった。
前半は各個人が本プログラムに参加してどう変化があったか、後半はチームとしてあった変化は何かをテーマとしながらもそれぞれのグループで自由な発言を求め、コミュニティビルディングを図った。
4)グループワーク「ネクストアクションを考える」
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
同席パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:箕輪町、阿賀野市、安来市
B:福山市、東海市、喜多方市
C:平内町、須賀川市、邑南町、田上町
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
同席パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:箕輪町、阿賀野市、安来市
B:福山市、東海市、喜多方市
C:平内町、須賀川市、邑南町、田上町
参加者の声(事後レビューから一部抜粋)
1)亀井先生の講義・トークセッション(1日目午前)を聞いて、これから「アジャイル政策」を作っていく上でどんな学びや気づきが得られましたか?印象に残ったキーワードを交えて記載してください。
○小さいステップをしれっと踏んで小さく失敗して、修正を重ねる。社会に働きかける、というフレーズに新鮮さを感じました。
○各専門職の専門性を理解することがとても重要だと思います。対話やディスカッションをする上では、各専門職の専門性を理解していないと話の深掘りもできなかったり、適切な議論ができないかと思います。
○行政の防衛的コミュニケーションからの脱却が必要だと思います!
2)コミュニティビルディング(2日目午前)を実施して、これからの自身の活動や自自治体の活動ついてどんな学びや気づき、考え方の変化がありましたか?できる限り詳しく教えてください。
○データではない町の実態や捉えている課題をチームで検討することで、言葉で表現できるようになってきた。また、人の意見を聞いて「なるほど!」感嘆したり、「それあるよね!」と共感できた。
○時代に変化してできる範囲内で微調整していくことを学びました。
○大きな変化ではなく、少しづつ変えていく、気がついたら、変わっていたくらいに自然に変えていくことが大事ということで、少し気が楽になった。
3)課題検討ワーク(1日目午後、2日目午後)を通じ、どんな気づきを得ましたか?あなたが感じたことを詳しく率直に教えてください。
○皆さん、苦しんでいるのが、よくわかります。みんな、同じです。
○重要度より緊急度で見た方がいいという指摘を頂きました。たしかに重要度で物事を見てしまうと、何事も欠けると困るものばかりで頭がパンクしてしまいます。緊急度の高いものから取り組むことを意識します。
○チーム皆で物事を考えていくと、優れたものができるということを実感した。
4)第4回の内容について、なんとなくモヤモヤしている点(腑に落ちていない、ぼんやりしている、考えを整理したい等)があれば教えてください。
○ロジックモデルを考えるときに、アクティビティと、アウトプット、アウトカムで行ったり来たりして、本当に満足したものができるか自信がない。アウトプットとアウトカムをしっかり区別できないような気がする。
○頭の中を言葉にすると10分の1になってしまい、字にするとさらに10分の1になってしまうということをまさにいま事後レビューを書いていて痛感しています。
○「ものさし」の決め方が、自分の周りでどうやって決めていけばいいのか、探し方のコツがあれば教えてもらいたいです。
5)第4回を踏まえて次回(第5回)そしてこれから(本プログラム終了後)どんなことに取り組みたいと思いますか?あなた個人の考えを聞かせてください。具体例があればそれも交えて詳しく教えてください。
○アジャイル政策を今回参加していない係員と共有したい。認知症施策を考えるのに使ってみたいと思う。
○SCさんととにかく一緒に動いてみる。
○まずは相談ツール、聞き取り票の作成と時間はかかりますが地域で使ってもらえる相談票を作成したいと思っています。
6)今後、本プログラム終了後、取り組みを進めていく上で不安なことや、メンターに支援して欲しいことなどあれば教えてください。
○今後、本プログラムが終了した後でも、今まで通り、チームでの話し合いや検討を重ねていけるか不安です。
○チームが集まって話をする時間を持つことができれば、少しずつでも前に進むことはできると思うので、不安などはないです。
○基本的には自分たちで頑張っていきたいと思いますが、もしすごく迷ったときがあれば、相談に乗っていただければ…
7)運営面で良かったこと、改善して欲しいことなどあれば教えてください。
○アジャイルプログラムは、毎回本当に勉強になります。この思考を参加していない他の職員に広げるためには、メンター的な役割を参加者が担いながら進めていくことが必要だと思います。このプログラムは参加できなくても音声が聞けるので、リアル感も感じながら補習できるのがとてもありがたいです。
○伝える事柄のイメージを例え話で伝えてくださるところがとてもわかりやすくて有り難いです。
○とても丁寧にフォローや運営をしてくださり、感謝ばかりです。
○zoomだけの研修でも良いのですが、長期間の研修のどこかのタイミングで、集合研修を1回ないしは2回ぐらいあると良い(大変と思いますが・・・)と私は思いました。
1)亀井先生の講義・トークセッション(1日目午前)を聞いて、これから「アジャイル政策」を作っていく上でどんな学びや気づきが得られましたか?印象に残ったキーワードを交えて記載してください。
○小さいステップをしれっと踏んで小さく失敗して、修正を重ねる。社会に働きかける、というフレーズに新鮮さを感じました。
○各専門職の専門性を理解することがとても重要だと思います。対話やディスカッションをする上では、各専門職の専門性を理解していないと話の深掘りもできなかったり、適切な議論ができないかと思います。
○行政の防衛的コミュニケーションからの脱却が必要だと思います!
2)コミュニティビルディング(2日目午前)を実施して、これからの自身の活動や自自治体の活動ついてどんな学びや気づき、考え方の変化がありましたか?できる限り詳しく教えてください。
○データではない町の実態や捉えている課題をチームで検討することで、言葉で表現できるようになってきた。また、人の意見を聞いて「なるほど!」感嘆したり、「それあるよね!」と共感できた。
○時代に変化してできる範囲内で微調整していくことを学びました。
○大きな変化ではなく、少しづつ変えていく、気がついたら、変わっていたくらいに自然に変えていくことが大事ということで、少し気が楽になった。
3)課題検討ワーク(1日目午後、2日目午後)を通じ、どんな気づきを得ましたか?あなたが感じたことを詳しく率直に教えてください。
○皆さん、苦しんでいるのが、よくわかります。みんな、同じです。
○重要度より緊急度で見た方がいいという指摘を頂きました。たしかに重要度で物事を見てしまうと、何事も欠けると困るものばかりで頭がパンクしてしまいます。緊急度の高いものから取り組むことを意識します。
○チーム皆で物事を考えていくと、優れたものができるということを実感した。
4)第4回の内容について、なんとなくモヤモヤしている点(腑に落ちていない、ぼんやりしている、考えを整理したい等)があれば教えてください。
○ロジックモデルを考えるときに、アクティビティと、アウトプット、アウトカムで行ったり来たりして、本当に満足したものができるか自信がない。アウトプットとアウトカムをしっかり区別できないような気がする。
○頭の中を言葉にすると10分の1になってしまい、字にするとさらに10分の1になってしまうということをまさにいま事後レビューを書いていて痛感しています。
○「ものさし」の決め方が、自分の周りでどうやって決めていけばいいのか、探し方のコツがあれば教えてもらいたいです。
5)第4回を踏まえて次回(第5回)そしてこれから(本プログラム終了後)どんなことに取り組みたいと思いますか?あなた個人の考えを聞かせてください。具体例があればそれも交えて詳しく教えてください。
○アジャイル政策を今回参加していない係員と共有したい。認知症施策を考えるのに使ってみたいと思う。
○SCさんととにかく一緒に動いてみる。
○まずは相談ツール、聞き取り票の作成と時間はかかりますが地域で使ってもらえる相談票を作成したいと思っています。
6)今後、本プログラム終了後、取り組みを進めていく上で不安なことや、メンターに支援して欲しいことなどあれば教えてください。
○今後、本プログラムが終了した後でも、今まで通り、チームでの話し合いや検討を重ねていけるか不安です。
○チームが集まって話をする時間を持つことができれば、少しずつでも前に進むことはできると思うので、不安などはないです。
○基本的には自分たちで頑張っていきたいと思いますが、もしすごく迷ったときがあれば、相談に乗っていただければ…
7)運営面で良かったこと、改善して欲しいことなどあれば教えてください。
○アジャイルプログラムは、毎回本当に勉強になります。この思考を参加していない他の職員に広げるためには、メンター的な役割を参加者が担いながら進めていくことが必要だと思います。このプログラムは参加できなくても音声が聞けるので、リアル感も感じながら補習できるのがとてもありがたいです。
○伝える事柄のイメージを例え話で伝えてくださるところがとてもわかりやすくて有り難いです。
○とても丁寧にフォローや運営をしてくださり、感謝ばかりです。
○zoomだけの研修でも良いのですが、長期間の研修のどこかのタイミングで、集合研修を1回ないしは2回ぐらいあると良い(大変と思いますが・・・)と私は思いました。
第3回
日時:2024年11月20日(水)、22日(金)
会場:オンライン
プログラム:「仲間をつくり、関係者を動かす」
<1日目>
トークセッション「課題に向けた関係者との協働を考える」
進 行 :松本小牧氏(愛知県豊明市市民生活部共生社会課)
プレゼンター:成田町子氏(愛知県豊明市健康福祉部長寿課 SC)
河﨑惠子氏(おたがいさまセンター「ちゃっと」)
グループワーク「わがまちの課題を検討する」
<2日目>
トークセッション「政策立案の技法 アジャイル型政策を実現するロジックモデルの作り方」
進 行 :松本小牧氏(愛知県豊明市市民生活部共生社会課)
プレゼンター:坂上遼氏 (愛知県豊明市市民生活部共生社会課)
鎌塚聡子氏(北海道深川市市民福祉部高齢者支援課)
グループワーク「ネクストアクションを考える」
=========================================================
会場:オンライン
プログラム:「仲間をつくり、関係者を動かす」
<1日目>
トークセッション「課題に向けた関係者との協働を考える」
進 行 :松本小牧氏(愛知県豊明市市民生活部共生社会課)
プレゼンター:成田町子氏(愛知県豊明市健康福祉部長寿課 SC)
河﨑惠子氏(おたがいさまセンター「ちゃっと」)
グループワーク「わがまちの課題を検討する」
<2日目>
トークセッション「政策立案の技法 アジャイル型政策を実現するロジックモデルの作り方」
進 行 :松本小牧氏(愛知県豊明市市民生活部共生社会課)
プレゼンター:坂上遼氏 (愛知県豊明市市民生活部共生社会課)
鎌塚聡子氏(北海道深川市市民福祉部高齢者支援課)
グループワーク「ネクストアクションを考える」
=========================================================
1)トークセッション「課題に向けた関係者との協働を考える」
トークセッション「課題に向けた関係者との協働を考える」
進 行 :松本小牧氏(愛知県豊明市市民生活部共生社会課)
プレゼンター:成田町子氏(愛知県豊明市健康福祉部長寿課 SC)
河﨑惠子氏(おたがいさまセンター「ちゃっと」)
愛知県豊明市の第1層SCと第2層SCの活動について聴講した。
「地域資源」とは何なのか。
「サロン」や「運動教室」をただ作れば良いのか。
住民主体の活動について今あるものをどう活用するか、ニーズに合わない場合はどうするか、SC(生活支援コーディネーター)として地域の生活を支援するとはどういうことか、を考えながら活動を行っている様子を1例として学んだ。
おたがいさまセンター「ちゃっと」は有償ボランティアの活動をシステム化して支援をしており、通常公的保険のヘルパーなどで賄えない「ちょっとした困りごと」を解決することを目指している。歳を取っても、忙しくても、「自分のできること」をお互いに補完しあって「おたがいさま」と支え合える仕組みの1例として知見を得た。
トークセッション「課題に向けた関係者との協働を考える」
進 行 :松本小牧氏(愛知県豊明市市民生活部共生社会課)
プレゼンター:成田町子氏(愛知県豊明市健康福祉部長寿課 SC)
河﨑惠子氏(おたがいさまセンター「ちゃっと」)
愛知県豊明市の第1層SCと第2層SCの活動について聴講した。
「地域資源」とは何なのか。
「サロン」や「運動教室」をただ作れば良いのか。
住民主体の活動について今あるものをどう活用するか、ニーズに合わない場合はどうするか、SC(生活支援コーディネーター)として地域の生活を支援するとはどういうことか、を考えながら活動を行っている様子を1例として学んだ。
おたがいさまセンター「ちゃっと」は有償ボランティアの活動をシステム化して支援をしており、通常公的保険のヘルパーなどで賄えない「ちょっとした困りごと」を解決することを目指している。歳を取っても、忙しくても、「自分のできること」をお互いに補完しあって「おたがいさま」と支え合える仕組みの1例として知見を得た。
2)グループワーク「わがまちの課題を検討する」
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、岩名礼介 氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
同席パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:箕輪町、阿賀野市、安来市
B:福山市、東海市、喜多方市
C:平内町、須賀川市、邑南町、田上町
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、岩名礼介 氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
同席パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:箕輪町、阿賀野市、安来市
B:福山市、東海市、喜多方市
C:平内町、須賀川市、邑南町、田上町
3)トークセッション「課題に向けた関係者との協働を考える」
トークセッション「課題に向けた関係者との協働を考える」
進 行 :松本小牧 氏(愛知県豊明市市民生活部共生社会課)
プレゼンター:坂上遼 氏 (愛知県豊明市市民生活部共生社会課)
鎌塚聡子 氏(北海道深川市市民福祉部高齢者支援課)
愛知県豊明市の重層支援担当部署の職員と昨年度の本事業参加自治体の北海道深川市の職員の活動について聴講した。
「コーディネートすること」について1日目に引き続き、2日目は「自治体職員として」の活動例を聴講した。
「この方が良いだろう」と準備していた支援が実際に支援を受けたい人のニーズに合っているか、ということを指摘され、活動を見直したエピソードや、実際に住民の困りごとを聞き、お互いに何が支援しあえるかを住民と一緒に確認し合って活動につなげたエピソードなどを聞いた。
トークセッション「課題に向けた関係者との協働を考える」
進 行 :松本小牧 氏(愛知県豊明市市民生活部共生社会課)
プレゼンター:坂上遼 氏 (愛知県豊明市市民生活部共生社会課)
鎌塚聡子 氏(北海道深川市市民福祉部高齢者支援課)
愛知県豊明市の重層支援担当部署の職員と昨年度の本事業参加自治体の北海道深川市の職員の活動について聴講した。
「コーディネートすること」について1日目に引き続き、2日目は「自治体職員として」の活動例を聴講した。
「この方が良いだろう」と準備していた支援が実際に支援を受けたい人のニーズに合っているか、ということを指摘され、活動を見直したエピソードや、実際に住民の困りごとを聞き、お互いに何が支援しあえるかを住民と一緒に確認し合って活動につなげたエピソードなどを聞いた。
4)グループワーク「ネクストアクションを考える」
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
同席パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:阿賀野市、安来市、箕輪町
B:喜多方市、東海市、福山市
C:平内町、須賀川市、邑南町、田上町
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
同席パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:阿賀野市、安来市、箕輪町
B:喜多方市、東海市、福山市
C:平内町、須賀川市、邑南町、田上町
参加者の声(事後レビューから一部抜粋)
1)豊明市のSCの動き(1日目午前)を聞いて、SCの活動や可能性についてどんな学びや気づきが得られましたか?印象に残ったキーワードを交えて記載してください。
○「高齢者が普通に暮らすために必要なものは、全て資源として考える」という言葉があったと思うのですが、それがとても印象に残っている。何か特別な活動、場所、環境を地域の資源と捉えがちだが、セッションを改めて聞き直し、考えてみると、確かに、何か特別なものが資源なのではなく、地域にもともとあるものが地域の資源なのだなと気付かされた。
○あらゆるものを地域資源ととらえるという考え方は大切であると感じた。また、協力者や仲間を増やすことで、地域資源というものが見えてくるのではないかと感じた。
○自分が楽しんで活動するということ、それが住民に伝わるということがよく理解できた。
○世の中にあるものすべてが資源だ、という言葉はとても印象に残りました。
2)自治体職員の活動(2日目午前)を聞いて、自身の活動や可能性についてどんな学びや気づき、考え方の変化がありましたか?できる限り詳しく教えてください。
○地域との顔の見える関係をつくり、地域の声、困っている人の声を聞いて、ニーズをきちんと把握した上で、地域の資源と結びつける、すごい仕事だと思いました。
○まず相手が利益を実感できるように働き掛け、その先にある自治体としての成果に結びつける、相互に助け合える関係性を様々な場面で構築できるよう、多くの方々と業種や立場を越えて信頼関係を構築することの大切さを改めて理解した。
○仕事ありきではなく、人ありきだということ。
3)課題検討ワーク(1日目午後、2日目午後)を通じ、どんな気づきを得ましたか?あなたが感じたことを詳しく率直に教えてください。
○繋ぐ先や社会資源を見つけるために、SCは地域を知ることが重要だと思いました。
○長らく迷走した当市の介護予防の取り組みですが、ようやくまとまりました。ほっとしてます。
○今更ですが担当内の共通認識は大切だと思いました。
○どこの市町村も総合事業に、介護予防に悩んでいると毎回ながら感じさせられます。
4)第3回の内容について、なんとなくモヤモヤしている点(腑に落ちていない、ぼんやりしている、考えを整理したい等)があれば教えてください。
○当市として同じところをぐるぐる回って本当に前進しているのか、手ごたえがつかめない。
○まわりと共有したり、いろんな場面で示せる価値観をしっかり持つというところがまだぼんやりとしている。
○当市でできるだろうかというところがモヤモヤしている。
○まだモヤモヤに行き着いていません。
○モヤモヤというより、皆さんが同じ方向向き出したことに安心した。
5)第3回を踏まえて次回(第4回)までにどんなことに取り組みたいと思いますか?あなた個人の考えを聞かせてください。具体例があればそれも交えて詳しく教えてください。
○もう一度第1回からの資料を読み返して、思考を整理してみたい。
○まずは自分自身でロジックモデルを考えてみて、課内・チーム内で共有していきたいと思います。
○まずは、他課の業務を教えてもらうことからはじめたいと思います。その前に何を聞くか、整理するつもりです。
○地域に出る機会を自粛していましたが、少しずつ出ていくようにしたいと思います。
6)今後、本プログラムを進める上で期待すること、不安に思うことなどを教えてください。
○すでに感じていますが、このプログラムの場だけに留まらず、プログラムで学んだ考え方を日ごろに活かすことができることです。
○このままで良いのだろうか。色々な事がモヤモヤします。
○それぞれの市町の悩みや課題に思っていることを聞くと、すごく共感する部分が多く、ロジックモデルが膨らんでしまいそうになりますが、わが町の課題を再確認し、それを解決するための方策を考えたいと思います。
○最終的な着地点がどこになるのか、私自身が見えていないことが不安です・・・
7)運営面で良かったこと、改善して欲しいことなどあれば教えてください。
○動画の配信は、再度見直すことも出来てとても嬉しい
○自分がモヤモヤしていることもあまり気づいていない時も、メンターの先生方には時間をかけて聞いていただくことで、自分の気持ちも整理できました。聞き出す力を勉強させていただいています。
○ZOOMではなく、直接会える機会ができるといいなと思います。
○メンタリングのタイムスケジュールをもう少し早くいただけると、他業務との調整ができ出席者が増えます。
○提出した資料だけでなく、その背景のプロセスについてもしっかりと認めてフィードバックしてくださることが嬉しいです。
1)豊明市のSCの動き(1日目午前)を聞いて、SCの活動や可能性についてどんな学びや気づきが得られましたか?印象に残ったキーワードを交えて記載してください。
○「高齢者が普通に暮らすために必要なものは、全て資源として考える」という言葉があったと思うのですが、それがとても印象に残っている。何か特別な活動、場所、環境を地域の資源と捉えがちだが、セッションを改めて聞き直し、考えてみると、確かに、何か特別なものが資源なのではなく、地域にもともとあるものが地域の資源なのだなと気付かされた。
○あらゆるものを地域資源ととらえるという考え方は大切であると感じた。また、協力者や仲間を増やすことで、地域資源というものが見えてくるのではないかと感じた。
○自分が楽しんで活動するということ、それが住民に伝わるということがよく理解できた。
○世の中にあるものすべてが資源だ、という言葉はとても印象に残りました。
2)自治体職員の活動(2日目午前)を聞いて、自身の活動や可能性についてどんな学びや気づき、考え方の変化がありましたか?できる限り詳しく教えてください。
○地域との顔の見える関係をつくり、地域の声、困っている人の声を聞いて、ニーズをきちんと把握した上で、地域の資源と結びつける、すごい仕事だと思いました。
○まず相手が利益を実感できるように働き掛け、その先にある自治体としての成果に結びつける、相互に助け合える関係性を様々な場面で構築できるよう、多くの方々と業種や立場を越えて信頼関係を構築することの大切さを改めて理解した。
○仕事ありきではなく、人ありきだということ。
3)課題検討ワーク(1日目午後、2日目午後)を通じ、どんな気づきを得ましたか?あなたが感じたことを詳しく率直に教えてください。
○繋ぐ先や社会資源を見つけるために、SCは地域を知ることが重要だと思いました。
○長らく迷走した当市の介護予防の取り組みですが、ようやくまとまりました。ほっとしてます。
○今更ですが担当内の共通認識は大切だと思いました。
○どこの市町村も総合事業に、介護予防に悩んでいると毎回ながら感じさせられます。
4)第3回の内容について、なんとなくモヤモヤしている点(腑に落ちていない、ぼんやりしている、考えを整理したい等)があれば教えてください。
○当市として同じところをぐるぐる回って本当に前進しているのか、手ごたえがつかめない。
○まわりと共有したり、いろんな場面で示せる価値観をしっかり持つというところがまだぼんやりとしている。
○当市でできるだろうかというところがモヤモヤしている。
○まだモヤモヤに行き着いていません。
○モヤモヤというより、皆さんが同じ方向向き出したことに安心した。
5)第3回を踏まえて次回(第4回)までにどんなことに取り組みたいと思いますか?あなた個人の考えを聞かせてください。具体例があればそれも交えて詳しく教えてください。
○もう一度第1回からの資料を読み返して、思考を整理してみたい。
○まずは自分自身でロジックモデルを考えてみて、課内・チーム内で共有していきたいと思います。
○まずは、他課の業務を教えてもらうことからはじめたいと思います。その前に何を聞くか、整理するつもりです。
○地域に出る機会を自粛していましたが、少しずつ出ていくようにしたいと思います。
6)今後、本プログラムを進める上で期待すること、不安に思うことなどを教えてください。
○すでに感じていますが、このプログラムの場だけに留まらず、プログラムで学んだ考え方を日ごろに活かすことができることです。
○このままで良いのだろうか。色々な事がモヤモヤします。
○それぞれの市町の悩みや課題に思っていることを聞くと、すごく共感する部分が多く、ロジックモデルが膨らんでしまいそうになりますが、わが町の課題を再確認し、それを解決するための方策を考えたいと思います。
○最終的な着地点がどこになるのか、私自身が見えていないことが不安です・・・
7)運営面で良かったこと、改善して欲しいことなどあれば教えてください。
○動画の配信は、再度見直すことも出来てとても嬉しい
○自分がモヤモヤしていることもあまり気づいていない時も、メンターの先生方には時間をかけて聞いていただくことで、自分の気持ちも整理できました。聞き出す力を勉強させていただいています。
○ZOOMではなく、直接会える機会ができるといいなと思います。
○メンタリングのタイムスケジュールをもう少し早くいただけると、他業務との調整ができ出席者が増えます。
○提出した資料だけでなく、その背景のプロセスについてもしっかりと認めてフィードバックしてくださることが嬉しいです。
第2回
日時:2024年10月15日(火)、16日(水)
会場:オンライン
プログラム:「高齢者の暮らしと地域課題」
<1日目>
模擬地域ケア会議「くらしの課題とは何かー地域ケア会議の体験」
進行:稲垣圭亮氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
グループワーク「わがまちの課題を検討する」
<2日目>
講義「政策立案の技法 アジャイル型政策を実現するロジックモデルの作り方」
亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
グループワーク「ネクストアクションを考える」
=========================================================
会場:オンライン
プログラム:「高齢者の暮らしと地域課題」
<1日目>
模擬地域ケア会議「くらしの課題とは何かー地域ケア会議の体験」
進行:稲垣圭亮氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
グループワーク「わがまちの課題を検討する」
<2日目>
講義「政策立案の技法 アジャイル型政策を実現するロジックモデルの作り方」
亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
グループワーク「ネクストアクションを考える」
=========================================================
1)模擬地域ケア会議「くらしの課題とは何かー地域ケア会議の体験」
進行:稲垣圭亮氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
愛知県豊明市で行われている「多職種ケアカンファレンス」で実際にあった2事例を基に「この事例『で』考える」ことに触れた。
それぞれの事例について事前に配布された事例情報をもとに「本人や家族の気持ち、置かれている状況について」を各々で想像し、「この事例が我がまちにいたら」という想定で「このケースは何が問題か、どんな支援が必要か、このケースを我が町で支援するとしたら何が課題か、我がまちに足りないもの(取組、資源)は何か」を考えた。
その後に実際に豊明市で行われた質疑・検討の様子を動画で供覧し、「この事例『で』考える」「この事例から(地域資源や他職種の知識を)学ぶ」ことを学んだ。
進行:稲垣圭亮氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
愛知県豊明市で行われている「多職種ケアカンファレンス」で実際にあった2事例を基に「この事例『で』考える」ことに触れた。
それぞれの事例について事前に配布された事例情報をもとに「本人や家族の気持ち、置かれている状況について」を各々で想像し、「この事例が我がまちにいたら」という想定で「このケースは何が問題か、どんな支援が必要か、このケースを我が町で支援するとしたら何が課題か、我がまちに足りないもの(取組、資源)は何か」を考えた。
その後に実際に豊明市で行われた質疑・検討の様子を動画で供覧し、「この事例『で』考える」「この事例から(地域資源や他職種の知識を)学ぶ」ことを学んだ。
2)グループワーク「わがまちの課題を検討する」
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
同席パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:箕輪町、阿賀野市、安来市
B:平内町、須賀川市、東海市
C:田上町、邑南町、福山市、喜多方市
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
同席パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:箕輪町、阿賀野市、安来市
B:平内町、須賀川市、東海市
C:田上町、邑南町、福山市、喜多方市
3)講義「政策立案の技法 アジャイル型政策を実現するロジックモデルの作り方」
講師:亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
ロジックモデルの作り方について講義を得た。
ロジックモデルは完成させることが目的ではない。
これまでに「個人で書き出して考える」としていたことを、より他人に伝えやすく、よりまとめやすくするための「手段」である。
都度書き換えられていくことは問題ない。
などの話があった。
講師:亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
ロジックモデルの作り方について講義を得た。
ロジックモデルは完成させることが目的ではない。
これまでに「個人で書き出して考える」としていたことを、より他人に伝えやすく、よりまとめやすくするための「手段」である。
都度書き換えられていくことは問題ない。
などの話があった。
4)グループワーク「これからの社会と基礎自治体職員」
講師:亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
同席パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:阿賀野市、箕輪町、安来市
B:須賀川市、平内町、東海市
C:邑南町、福山市、喜多方市、田上町
講師:亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
同席パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:阿賀野市、箕輪町、安来市
B:須賀川市、平内町、東海市
C:邑南町、福山市、喜多方市、田上町
参加者の声(事後レビューから一部抜粋)
1)模擬ケア会議(1日目午前)で新たにどんな学びや気づきが得られましたか?できる限り詳しく教えてください。
○個別事例から地域課題をかんがえるときに、我がまちで支援するなら何が課題かと、発想を展開する作業が自分は不得意だと感じました。社会資源も支援するマンパワーも少ない我が町で、つい個々の対応に追われて、なんとかなったから良かったーと、ほっとして終了してしまいがちですが、これだと変わらないですね…
○模擬ケア会議では、実際にその方のケースに携わってはいませんが、今までのあらゆる知識などをグループで出し合うことで、色んな新しい物事の見方などが見えてくるような気がしました。
○事例で考えることで、地域の課題を考える
○初めてのことで、何から考えたらいいか分からなかったけど、限られた情報からいろんなことを想像することが大切で、実際には声にならない声を聞いていくことが大切なんだろうなと思いました。
2)講義(2日目午前)で新たにどんな学びや気づきが得られましたか?印象に残ったキーワードを交えて詳しく記載してください。
○これまで関わった業務では内容的に必要性と効率が重要で「効果」は二の次とすることが多かった。「有効性」が重要というところがわかってはいるけれどなかなかできていない。
○行ったり来たりの志向が重要であるという学びを得ました。また、PDCAサイクルの回し方について1事業という大きな単位で考えるのではなく、1事業内の小さな単位で細かく、頻度を上げて繰り返すことが今まで自分の中に無かった視点で大変勉強になりました。
○ロジックモデルに落とすことで自分の中での自問自答ができると感じる。
3)課題検討ワーク(1日目午後、2日目午後)を通じ、どんな気づきを得ましたか?あなたが感じたことを詳しく率直に教えてください。
○毎回、頭パンクです。まさかの視点が来るので正直理解するのに時間を要します。
○日頃保健事業では把握しているのに今回のワークで忘れていた視点として、対象としている人たちが、町のどれくらいの規模なのかということだった。この視点がないと打ち手が定まらず実現するための財政確保も、関係者や地域の理解も得にくいということを改めて感じた。
○やむを得なく転出する高齢者の数について深く考えたことがなかったので、新たな視点を得られました。
4)第2回の内容について、なんとなくモヤモヤしている点(腑に落ちていない、ぼんやりしている、考えを整理したい等)があれば教えてください。
○少しずつ、チーム内のそれぞれのスタンスなどの共有もできてきていると思うので良い方向に向かっていると思います。
○もやもやしているというか、どのくらいのペースでやればいいのかがわからなくて焦りを感じます。
○たくさんのことを言われて、平常業務もある中で何がわからないのかがわからなくなっている。
○もやもやは存在しますが言語化がまだできません。
5)第2回を踏まえて次回(第3回)までにどんなことに取り組みたいと思いますか?あなた個人の考えを聞かせてください。具体例があればそれも交えて詳しく教えてください。
○1人でも2人でも話を聞きにいくこと。
○そもそもの制度理解をチーム内で進める必要性がある。
○まずは、包括さんや専門職の方への聞き取りについて、役割分担したいと思います。
6)今後、本プログラムを進める上で期待すること、不安に思うことなどを教えてください。
○チームで取り組むことで、課として成長できるとよいと思う。
○新たな取り組み方法、考え方の知識を得ながら、具体的な取り組みを進めていける手応えを感じ始めていますので、今後ともプログラム内容に期待しています。
○プログラムが終わった後でも自分たちでやっていけるのかが不安です。
7)運営面で良かったこと、改善して欲しいことなどあれば教えてください。
○スムーズな運営でとても助かります。
○画面越しでも意見をしっかりと聞いてくれていることやその雰囲気がよく伝わってきて安心して発言ができます。
○フォローアップも含め、毎回親身で有難いです。
○最初は、このレポートが負担でしたが、最近は慣れてきて自分の振り返りに必要な作業だと思っています。
1)模擬ケア会議(1日目午前)で新たにどんな学びや気づきが得られましたか?できる限り詳しく教えてください。
○個別事例から地域課題をかんがえるときに、我がまちで支援するなら何が課題かと、発想を展開する作業が自分は不得意だと感じました。社会資源も支援するマンパワーも少ない我が町で、つい個々の対応に追われて、なんとかなったから良かったーと、ほっとして終了してしまいがちですが、これだと変わらないですね…
○模擬ケア会議では、実際にその方のケースに携わってはいませんが、今までのあらゆる知識などをグループで出し合うことで、色んな新しい物事の見方などが見えてくるような気がしました。
○事例で考えることで、地域の課題を考える
○初めてのことで、何から考えたらいいか分からなかったけど、限られた情報からいろんなことを想像することが大切で、実際には声にならない声を聞いていくことが大切なんだろうなと思いました。
2)講義(2日目午前)で新たにどんな学びや気づきが得られましたか?印象に残ったキーワードを交えて詳しく記載してください。
○これまで関わった業務では内容的に必要性と効率が重要で「効果」は二の次とすることが多かった。「有効性」が重要というところがわかってはいるけれどなかなかできていない。
○行ったり来たりの志向が重要であるという学びを得ました。また、PDCAサイクルの回し方について1事業という大きな単位で考えるのではなく、1事業内の小さな単位で細かく、頻度を上げて繰り返すことが今まで自分の中に無かった視点で大変勉強になりました。
○ロジックモデルに落とすことで自分の中での自問自答ができると感じる。
3)課題検討ワーク(1日目午後、2日目午後)を通じ、どんな気づきを得ましたか?あなたが感じたことを詳しく率直に教えてください。
○毎回、頭パンクです。まさかの視点が来るので正直理解するのに時間を要します。
○日頃保健事業では把握しているのに今回のワークで忘れていた視点として、対象としている人たちが、町のどれくらいの規模なのかということだった。この視点がないと打ち手が定まらず実現するための財政確保も、関係者や地域の理解も得にくいということを改めて感じた。
○やむを得なく転出する高齢者の数について深く考えたことがなかったので、新たな視点を得られました。
4)第2回の内容について、なんとなくモヤモヤしている点(腑に落ちていない、ぼんやりしている、考えを整理したい等)があれば教えてください。
○少しずつ、チーム内のそれぞれのスタンスなどの共有もできてきていると思うので良い方向に向かっていると思います。
○もやもやしているというか、どのくらいのペースでやればいいのかがわからなくて焦りを感じます。
○たくさんのことを言われて、平常業務もある中で何がわからないのかがわからなくなっている。
○もやもやは存在しますが言語化がまだできません。
5)第2回を踏まえて次回(第3回)までにどんなことに取り組みたいと思いますか?あなた個人の考えを聞かせてください。具体例があればそれも交えて詳しく教えてください。
○1人でも2人でも話を聞きにいくこと。
○そもそもの制度理解をチーム内で進める必要性がある。
○まずは、包括さんや専門職の方への聞き取りについて、役割分担したいと思います。
6)今後、本プログラムを進める上で期待すること、不安に思うことなどを教えてください。
○チームで取り組むことで、課として成長できるとよいと思う。
○新たな取り組み方法、考え方の知識を得ながら、具体的な取り組みを進めていける手応えを感じ始めていますので、今後ともプログラム内容に期待しています。
○プログラムが終わった後でも自分たちでやっていけるのかが不安です。
7)運営面で良かったこと、改善して欲しいことなどあれば教えてください。
○スムーズな運営でとても助かります。
○画面越しでも意見をしっかりと聞いてくれていることやその雰囲気がよく伝わってきて安心して発言ができます。
○フォローアップも含め、毎回親身で有難いです。
○最初は、このレポートが負担でしたが、最近は慣れてきて自分の振り返りに必要な作業だと思っています。
第1回
日時:2024年9月17日(火)、19日(木)
会場:オンライン
プログラム:「基礎自治体の役割価値と可能性」
<1日目>
講義「これからの社会と基礎自治体職員」
亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
グループワーク「ダイアローグ(対話)」
グループワーク「わがまちの課題を検討する」
<2日目>
講義「基礎自治体における「課題」とその解決」
亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
グループワーク「ネクストアクションを考える」
=========================================================
会場:オンライン
プログラム:「基礎自治体の役割価値と可能性」
<1日目>
講義「これからの社会と基礎自治体職員」
亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
グループワーク「ダイアローグ(対話)」
グループワーク「わがまちの課題を検討する」
<2日目>
講義「基礎自治体における「課題」とその解決」
亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
グループワーク「ネクストアクションを考える」
=========================================================
1)講義「これからの社会と基礎自治体職員」
講師:亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
基礎自治体職員の役割とは。
「この地域におけるそれぞれの日々の暮らしを、制度の運用や事業、市民社会の相互支援の機能を通じて、支えることができる」と言うことではないか。自治体職員として市民を支えていることは何か、一市民として支えられていることは何か。実際はどうだろうかと参加者それぞれが我が事として考えたり、実感を持って理解が進められるような内容で、そのための専門性を育てていく必要性、多様な関係者を動かしていくためのコミュにケーションのあり方等について知見を得た。
資料の画面共有をせず、画面上の聴講者の反応を逐次確認し、時には呼びかけながら講義を進められた。
講師:亀井善太郎氏(PHP総研 主席研究員)
基礎自治体職員の役割とは。
「この地域におけるそれぞれの日々の暮らしを、制度の運用や事業、市民社会の相互支援の機能を通じて、支えることができる」と言うことではないか。自治体職員として市民を支えていることは何か、一市民として支えられていることは何か。実際はどうだろうかと参加者それぞれが我が事として考えたり、実感を持って理解が進められるような内容で、そのための専門性を育てていく必要性、多様な関係者を動かしていくためのコミュにケーションのあり方等について知見を得た。
資料の画面共有をせず、画面上の聴講者の反応を逐次確認し、時には呼びかけながら講義を進められた。
2)グループワーク「ダイアローグ(対話)」
3)グループワーク「わがまちの課題を検討する」
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:岩名礼介 氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)
同席パートナー
A:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
B:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:箕輪町、安来市、阿賀野市
B:福山市、田上町、東海市
C:喜多方市、平内町、邑南町、須賀川市
午前中の講義を受けて、個々人がどう感じたか、チームメンバー及びメンターに共有した。
それぞれが言葉にすることで、「あの人はそう感じたんだ」「この人と同じように思った」など気づき、発見、共感などを得て、言葉にしてコミュニケーションをとることの重要性を学んだ。
3)グループワーク「わがまちの課題を検討する」
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
池田寛 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:岩名礼介 氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)
同席パートナー
A:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
B:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:箕輪町、安来市、阿賀野市
B:福山市、田上町、東海市
C:喜多方市、平内町、邑南町、須賀川市
午前中の講義を受けて、個々人がどう感じたか、チームメンバー及びメンターに共有した。
それぞれが言葉にすることで、「あの人はそう感じたんだ」「この人と同じように思った」など気づき、発見、共感などを得て、言葉にしてコミュニケーションをとることの重要性を学んだ。
4)講義「基礎自治体における「課題」とその解決」
講師 :亀井善太郎氏(PHP総研)
講師 :亀井善太郎氏(PHP総研)
5)グループワーク「ネクストアクションを考える」
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:岩名礼介 氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、 高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)
同席パートナー
A:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
B:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:安来市、箕輪町、阿賀野市
B:田上町、福山市、東海市
C:平内町、邑南町、喜多方市、須賀川市
担当メンター
A:服部真治 氏(医療経済研究機構)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:岩名礼介 氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、 高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)
同席パートナー
A:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
B:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加自治体振り分け
A:安来市、箕輪町、阿賀野市
B:田上町、福山市、東海市
C:平内町、邑南町、喜多方市、須賀川市
参加者の声(事後レビューから一部抜粋)
1)講義(1日目午前、2日目午前)で新たにどんな学びや気づきが得られましたか?印象に残ったキーワードを交えて記載してください。
○今まで町民のために、という行政意識は持ってはいたものの、社会福祉士としての専門性ばかりを重視していたことに気付かされました。
○市民の事を考えてるようで、本当につまずいている人たちを見ることができていなかった。課題を設定するのは、つまずいている人たちを見ることから始まることに気づけた。
○今まで、課題を考える時に、事業の課題ばかり考えていたことに気づかされました。制度や事業はツールとして使うもの。誰がどんなことにつまづき、困っているのかに視点を置いて考えることが大切。
2)課題検討ワーク(1日目午後、2日目午後)を通じ、どんな気づきを得ましたか?あなたが感じたことを率直に教えてください。
○総合事業の基本がわかっていない。何となく慣習に流されている。
○それぞれに感じている課題がバラバラだった事に気づけました。
○『事業ありき』という言葉をどこか他人事に思っていた。どんな人がどんなことに困っているのか、本当の課題は何か掘り下げることが必要ということ。
3)第1回の内容について、なんとなくモヤモヤしている点(腑に落ちていない、ぼんやりしている、考えを整理したい等)があれば教えてください。
○どこに課題があるのか、本質をどうとらえると捉えたことになるのか想像がつかない。
○随所にチーム力とコミュニケーションの必要性のお話しがありましたが、組織の異なる方とのチームワークの難しさを日々感じており、どのようにうごけばその溝が埋まるのかと思っています。
○チーム内でとりあえずそれぞれの違いがわかったことが有意義でした。さあ、やっとアジャイルに取り掛かろうかいうスタンスに立つことができたと思います。
4)第1回を踏まえて次回(第2回)までにどんなことに取り組みたいと思いますか?あなた個人の考えを聞かせてください。
○個人で考えてみる。できるだけデータを集めて、チームと共有。指示された作業に集中したいと思います。
○まずは、課題を見える化するために自分が担当している事業の参加者や地域参加率などを表にしてから、どこが課題なのかを考えていきたい。
○うまくいったケースとうまくいかなかったケースの仕分け。チームメンバーの専門性を探す。
5)今後、本プログラムを進める上で期待すること、不安に思うことなどを教えてください。
○チームでコミュニケーションをし、先生方とのメンタリングで考え方の視点に気づきをもらえ、次にやることがしっかりと見えてくるので、今後どう進めていけるのか自分の気付きが増えると思うので、楽しみです。
○せっかくアドバイスをいただいているのに、自分がその助言についていけてるか不安です。
○今後の進め方や、社協との付き合い方など、今までとは違う視点が持てていると感じています。
6)運営面で良かったこと、改善して欲しいことなどあれば教えてください。
○連続2日間はなかなか厳しい
○早い段階での懇親会などを通じて、やり取りのハードルを下げることができたのは良かったです。
○事務局の方々の影の支援に感謝します。
○とてもよい雰囲気のなかで、プログラムに参加できています。
1)講義(1日目午前、2日目午前)で新たにどんな学びや気づきが得られましたか?印象に残ったキーワードを交えて記載してください。
○今まで町民のために、という行政意識は持ってはいたものの、社会福祉士としての専門性ばかりを重視していたことに気付かされました。
○市民の事を考えてるようで、本当につまずいている人たちを見ることができていなかった。課題を設定するのは、つまずいている人たちを見ることから始まることに気づけた。
○今まで、課題を考える時に、事業の課題ばかり考えていたことに気づかされました。制度や事業はツールとして使うもの。誰がどんなことにつまづき、困っているのかに視点を置いて考えることが大切。
2)課題検討ワーク(1日目午後、2日目午後)を通じ、どんな気づきを得ましたか?あなたが感じたことを率直に教えてください。
○総合事業の基本がわかっていない。何となく慣習に流されている。
○それぞれに感じている課題がバラバラだった事に気づけました。
○『事業ありき』という言葉をどこか他人事に思っていた。どんな人がどんなことに困っているのか、本当の課題は何か掘り下げることが必要ということ。
3)第1回の内容について、なんとなくモヤモヤしている点(腑に落ちていない、ぼんやりしている、考えを整理したい等)があれば教えてください。
○どこに課題があるのか、本質をどうとらえると捉えたことになるのか想像がつかない。
○随所にチーム力とコミュニケーションの必要性のお話しがありましたが、組織の異なる方とのチームワークの難しさを日々感じており、どのようにうごけばその溝が埋まるのかと思っています。
○チーム内でとりあえずそれぞれの違いがわかったことが有意義でした。さあ、やっとアジャイルに取り掛かろうかいうスタンスに立つことができたと思います。
4)第1回を踏まえて次回(第2回)までにどんなことに取り組みたいと思いますか?あなた個人の考えを聞かせてください。
○個人で考えてみる。できるだけデータを集めて、チームと共有。指示された作業に集中したいと思います。
○まずは、課題を見える化するために自分が担当している事業の参加者や地域参加率などを表にしてから、どこが課題なのかを考えていきたい。
○うまくいったケースとうまくいかなかったケースの仕分け。チームメンバーの専門性を探す。
5)今後、本プログラムを進める上で期待すること、不安に思うことなどを教えてください。
○チームでコミュニケーションをし、先生方とのメンタリングで考え方の視点に気づきをもらえ、次にやることがしっかりと見えてくるので、今後どう進めていけるのか自分の気付きが増えると思うので、楽しみです。
○せっかくアドバイスをいただいているのに、自分がその助言についていけてるか不安です。
○今後の進め方や、社協との付き合い方など、今までとは違う視点が持てていると感じています。
6)運営面で良かったこと、改善して欲しいことなどあれば教えてください。
○連続2日間はなかなか厳しい
○早い段階での懇親会などを通じて、やり取りのハードルを下げることができたのは良かったです。
○事務局の方々の影の支援に感謝します。
○とてもよい雰囲気のなかで、プログラムに参加できています。
オリエンテーション
日時:2024年8月21日(水)
会場:オンライン
プログラム:開講式
主催者挨拶 都築晃氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
行政説明 小西雄樹氏(厚生労働省老健局総務課 課長補佐)
コミュニティビルディング1
参加自治体の自己紹介
進行:池田寛氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
メンタリング体験(昨年参加自治体のメンタリング見学)
進行:都築晃氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
コミュニティビルディング2
グループワーク「わがまちの課題を検討する」
本プログラムは厚生労働省老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた市町村の地域デザイン力を高める共創コミュニティによる支援に関する調査研究」の一環として実施しているため、行政説明として小西氏(厚生労働省老健局総務課 課長補佐)より、事業の位置付け、期待されることについて話があった。
参加自治体の簡単な自己紹介をし、全体でどのような自治体が参加しているのか把握した。
本プログラムの肝である「メンタリング」を実感していただくため、一昨年度・昨年度参加自治体の協力のもと、プログラムのその後について紹介いただきメンタリングを行った。
午後はグループワークにて各参加自治体から問題意識、意気込み、参加のきっかけなどアピールを行った。
=========================================================
会場:オンライン
プログラム:開講式
主催者挨拶 都築晃氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
行政説明 小西雄樹氏(厚生労働省老健局総務課 課長補佐)
コミュニティビルディング1
参加自治体の自己紹介
進行:池田寛氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
メンタリング体験(昨年参加自治体のメンタリング見学)
進行:都築晃氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
コミュニティビルディング2
グループワーク「わがまちの課題を検討する」
本プログラムは厚生労働省老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた市町村の地域デザイン力を高める共創コミュニティによる支援に関する調査研究」の一環として実施しているため、行政説明として小西氏(厚生労働省老健局総務課 課長補佐)より、事業の位置付け、期待されることについて話があった。
参加自治体の簡単な自己紹介をし、全体でどのような自治体が参加しているのか把握した。
本プログラムの肝である「メンタリング」を実感していただくため、一昨年度・昨年度参加自治体の協力のもと、プログラムのその後について紹介いただきメンタリングを行った。
午後はグループワークにて各参加自治体から問題意識、意気込み、参加のきっかけなどアピールを行った。
=========================================================
1)参加自治体の自己紹介
進行:池田寛氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
各自治体から1分程度でそれぞれの市町村概要をお伝えいただいた。
進行:池田寛氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
各自治体から1分程度でそれぞれの市町村概要をお伝えいただいた。
2)メンタリング体験
進行:都築晃氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
一昨年度・昨年度参加自治体(呼びかけて集まった自治体:兵庫県赤穂市、新潟県出雲崎町、北海道深川市)に終了時から現在の進捗について報告いただき、メンタリングを行った。その様子を今年度参加自治体に見ていただき、メンタリングとはどのように進んでいくものか、メンターとの関係性を体験する時間とした。
進行:都築晃氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
一昨年度・昨年度参加自治体(呼びかけて集まった自治体:兵庫県赤穂市、新潟県出雲崎町、北海道深川市)に終了時から現在の進捗について報告いただき、メンタリングを行った。その様子を今年度参加自治体に見ていただき、メンタリングとはどのように進んでいくものか、メンターとの関係性を体験する時間とした。
3)グループワーク「わがまちの課題を検討する」
担当メンター
A:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:岩名礼介 氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
担当パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加市町村振り分け
A:須賀川市、阿賀野市、田上町、安来市
B:平内町、箕輪町、豊中市
C:喜多方市、東海市、邑南町、福山市
エントリーシートの内容をもとに、参加のきっかけや、今取り組んでいること、問題意識などを共有し、メンターからの問いかけにより潜在的な問題意識を言語化するように働きかけた。
担当メンター
A:高橋拓朗 氏(NTTデータ経営研究所)、都築晃 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:岩名礼介 氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)、三原岳 氏(ニッセイ基礎研究所)
C:亀井善太郎 氏(PHP総研)、松本小牧 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
担当パートナー
A:稲垣圭亮 氏(藤田医科大学地域包括ケア中核センター)
B:竹田哲規 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
C:坂上遼 氏(豊明市市民生活部共生社会課)
参加市町村振り分け
A:須賀川市、阿賀野市、田上町、安来市
B:平内町、箕輪町、豊中市
C:喜多方市、東海市、邑南町、福山市
エントリーシートの内容をもとに、参加のきっかけや、今取り組んでいること、問題意識などを共有し、メンターからの問いかけにより潜在的な問題意識を言語化するように働きかけた。
参加者の声(事後レビューから一部抜粋)
1)一昨年度、昨年度参加自治体メンタリングでどんな印象を持ちましたか?感じたこと、気づいたこと、学びとなったこと等、印象に残ったキーワードを交えて記載してください。
○参加された皆さんが生き生きと発表されていて、一皮むけた感というか充実感が伝わって実り多いものだったんだろうと感じました。休憩時間のメンターさんとのやりとりも和気あいあいとしていて信頼関係ができているんだろうなと感じました。
○紆余曲折もたくさん経たと思いますが、表情がすっきり明るく、目の前の課題もクリアになっている印象でした。
○メンターの方とフレンドリーな雰囲気がとても印象的でした。
2)わがまちについてメンターと話をしてみて、どんな印象を持ちましたか?感じたこと、気づいたこと、学びとなったこと等、印象に残ったキーワードを交えて記載してください。
○自分のまちについて強みや足りないところについて理解して自信を持ってアウトプットできていないと感じました。
○こんなに集中して話していただけると思っておらず、チームでも話しているつもりでしたがまだまだ足りないと思いました。
○若干緊張もありましたがとても話しやすく、気が楽になりました。
○わがまち、については、みんなの思いが聞け、それぞれがどう感じているのかがわかりました。
3)今後検討しようとするテーマやわがまちの課題について、迷っていることやモヤモヤしている点を教えてください。
○事業の見直しが必要だか、どこに焦点をあて、どこに向かっていけばいいのか、定まらない。
○行政の立場で進めて実施してきた事業が、本当に住民の健康のためになっているのか、意味のあることを行っているかわからずモヤモヤする。まちの課題がずれているのではないかという思いがある。
○住民さんの安心ってなんだろう?町に期待してることって何だろう?どうなれば自分たちは、うまくいったと思えるのだろう。私達は、何に疲れているのだろう?
4)次回(第1回)までにどんなことをまでにどんなことをやってみたいと思いますか?あなた個人の考えを聞かせてください。
○高齢者の不安は何か、いつから不安になるのかを探る
○どんな事をやってみたいか?正直何もわからず、何も思いつきません。
○頭の中を整理したいです。
5)本プログラムの参加にあたり、楽しみにしていることや、不安なことを教えてください。
○課題解決に向けたプロセスが学べること
○色々な方からの考え方の視点を知ることが楽しみです。
○このプログラムを通じて職員の政策形成能力が今以上に向上してほしい。逆に悩んだり、手詰まり感で気持ちが苦しくならないかとも思う。
6)運営面で良かったこと、改善して欲しいことなどあれば教えてください。
○オリエンテーションが長いと感じた。
○teamsでやることは、デジタルツールが苦手な職員が多いので、DXのOJTみたいで良いです。
○皆さんがとても気さくでわかりやすい説明をしていただけるので参加者は緊張せずに参加することができる為とても良いと感じました。
○自分たちの中で整理しきれてない考えなどを要約、言語化していただけることが有難いです。
1)一昨年度、昨年度参加自治体メンタリングでどんな印象を持ちましたか?感じたこと、気づいたこと、学びとなったこと等、印象に残ったキーワードを交えて記載してください。
○参加された皆さんが生き生きと発表されていて、一皮むけた感というか充実感が伝わって実り多いものだったんだろうと感じました。休憩時間のメンターさんとのやりとりも和気あいあいとしていて信頼関係ができているんだろうなと感じました。
○紆余曲折もたくさん経たと思いますが、表情がすっきり明るく、目の前の課題もクリアになっている印象でした。
○メンターの方とフレンドリーな雰囲気がとても印象的でした。
2)わがまちについてメンターと話をしてみて、どんな印象を持ちましたか?感じたこと、気づいたこと、学びとなったこと等、印象に残ったキーワードを交えて記載してください。
○自分のまちについて強みや足りないところについて理解して自信を持ってアウトプットできていないと感じました。
○こんなに集中して話していただけると思っておらず、チームでも話しているつもりでしたがまだまだ足りないと思いました。
○若干緊張もありましたがとても話しやすく、気が楽になりました。
○わがまち、については、みんなの思いが聞け、それぞれがどう感じているのかがわかりました。
3)今後検討しようとするテーマやわがまちの課題について、迷っていることやモヤモヤしている点を教えてください。
○事業の見直しが必要だか、どこに焦点をあて、どこに向かっていけばいいのか、定まらない。
○行政の立場で進めて実施してきた事業が、本当に住民の健康のためになっているのか、意味のあることを行っているかわからずモヤモヤする。まちの課題がずれているのではないかという思いがある。
○住民さんの安心ってなんだろう?町に期待してることって何だろう?どうなれば自分たちは、うまくいったと思えるのだろう。私達は、何に疲れているのだろう?
4)次回(第1回)までにどんなことをまでにどんなことをやってみたいと思いますか?あなた個人の考えを聞かせてください。
○高齢者の不安は何か、いつから不安になるのかを探る
○どんな事をやってみたいか?正直何もわからず、何も思いつきません。
○頭の中を整理したいです。
5)本プログラムの参加にあたり、楽しみにしていることや、不安なことを教えてください。
○課題解決に向けたプロセスが学べること
○色々な方からの考え方の視点を知ることが楽しみです。
○このプログラムを通じて職員の政策形成能力が今以上に向上してほしい。逆に悩んだり、手詰まり感で気持ちが苦しくならないかとも思う。
6)運営面で良かったこと、改善して欲しいことなどあれば教えてください。
○オリエンテーションが長いと感じた。
○teamsでやることは、デジタルツールが苦手な職員が多いので、DXのOJTみたいで良いです。
○皆さんがとても気さくでわかりやすい説明をしていただけるので参加者は緊張せずに参加することができる為とても良いと感じました。
○自分たちの中で整理しきれてない考えなどを要約、言語化していただけることが有難いです。
オープンセミナー
日時:2024年7月9日(火)
会場:オンライン
プログラム:講演:「包括的支援体制/重層的支援体制整備について知り、地域包括ケアシステムの明日を考える 」
岩名礼介氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
メンタートークセッション
<モデレーター>
三原岳氏(ニッセイ基礎研究所)
<登壇者>
岩名礼介氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
松本小牧氏(豊明市市民生活部共生社会課)
事務連絡 アジャイル型地域包括ケア政策共創プログラム2024について(参加自治体募集について)
=========================================================
会場:オンライン
プログラム:講演:「包括的支援体制/重層的支援体制整備について知り、地域包括ケアシステムの明日を考える 」
岩名礼介氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
メンタートークセッション
<モデレーター>
三原岳氏(ニッセイ基礎研究所)
<登壇者>
岩名礼介氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
松本小牧氏(豊明市市民生活部共生社会課)
事務連絡 アジャイル型地域包括ケア政策共創プログラム2024について(参加自治体募集について)
=========================================================
1)講演:「包括的支援体制/重層的支援体制整備について知り、地域包括ケアシステムの明日を考える 」
講師 :岩名礼介 氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
「地域包括ケア」と「包括的支援体制」「重層的支援体制整備」がどう関係するのか。
この2つの体制を理解することで、地域包括ケアをどうしていくかを考えるというテーマで話が進められた。
役所の窓口に相談があった時、「制度に当てはまらないのでできません」というだけの対応になっていないか。
役所にまで来るという状況はその人がどのような状態にあるのか、助けを求めてきたのでないか、などの想像力を働かせた時に、現行制度は当てはまらないが、何か手を差し伸べられるものはないのかと「ケースワーク」することが大切である。
それに対して対応するために、それぞれの支援体制を利用して様々なことを検討するという方法が考えられる。
また、支援がしやすい「地域づくり」も重要であり、下支えしてくれる地域、地域と協働して活動する行政、それぞれがうまく噛み合って制度以外の支援も含めて「包括的な支援体制」が実施することができるのではないか。
「包括的な支援体制」の実施は努力義務となっている。一方で「重層的支援体制整備」は任意事業である。
「重層的支援体制」は整備されなくとも「包括的な支援体制」は実施することができる。
それぞれの狭間になる事項をそれぞれが支え合って調整しあうことで「包括的に」支援できることを目指してはどうか。
講師 :岩名礼介 氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
「地域包括ケア」と「包括的支援体制」「重層的支援体制整備」がどう関係するのか。
この2つの体制を理解することで、地域包括ケアをどうしていくかを考えるというテーマで話が進められた。
役所の窓口に相談があった時、「制度に当てはまらないのでできません」というだけの対応になっていないか。
役所にまで来るという状況はその人がどのような状態にあるのか、助けを求めてきたのでないか、などの想像力を働かせた時に、現行制度は当てはまらないが、何か手を差し伸べられるものはないのかと「ケースワーク」することが大切である。
それに対して対応するために、それぞれの支援体制を利用して様々なことを検討するという方法が考えられる。
また、支援がしやすい「地域づくり」も重要であり、下支えしてくれる地域、地域と協働して活動する行政、それぞれがうまく噛み合って制度以外の支援も含めて「包括的な支援体制」が実施することができるのではないか。
「包括的な支援体制」の実施は努力義務となっている。一方で「重層的支援体制整備」は任意事業である。
「重層的支援体制」は整備されなくとも「包括的な支援体制」は実施することができる。
それぞれの狭間になる事項をそれぞれが支え合って調整しあうことで「包括的に」支援できることを目指してはどうか。
2)トークセッション
<モデレーター> 三原岳氏(ニッセイ基礎研究所)
<登壇者> 岩名礼介氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
松本小牧氏(豊明市市民生活部共生社会課)
視聴者から公開講座で話があった重層的支援に対して実施状況や考えを即時的にアンケートをとり、話が進められた。
これまで高齢者支援分野、障害支援分野が行なってきたことと重層的支援がどのように関わるのか。全世代、家庭丸ごとが対象となる「包括的な支援」と「地域包括ケア」の関係性を見直した。
引き続いて本事業へエントリーするにあたってのよくある質問を登壇メンターと共に回答した。
本内容はこちらから閲覧可能です。
<モデレーター> 三原岳氏(ニッセイ基礎研究所)
<登壇者> 岩名礼介氏(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)
松本小牧氏(豊明市市民生活部共生社会課)
視聴者から公開講座で話があった重層的支援に対して実施状況や考えを即時的にアンケートをとり、話が進められた。
これまで高齢者支援分野、障害支援分野が行なってきたことと重層的支援がどのように関わるのか。全世代、家庭丸ごとが対象となる「包括的な支援」と「地域包括ケア」の関係性を見直した。
引き続いて本事業へエントリーするにあたってのよくある質問を登壇メンターと共に回答した。
本内容はこちらから閲覧可能です。